
 嵍偐傜乽奐尦捠曮乿乽榓摨奐噍乿乮摵惢丒暋惢乯乽晉杮慘乿乮暋惢乯
嵍偐傜乽奐尦捠曮乿乽榓摨奐噍乿乮摵惢丒暋惢乯乽晉杮慘乿乮暋惢乯晉杮慘偼彽暉偺堊偵丄枖丄榓摨奐噍偼暯忛嫗憿塩偺堊偺嵿尮偲偟偰偦傟偧傟拻憿偝傟偨丅偙傟傜偼丄奆堦條偵摨偠戝偒偝偱偁傞丅摵慘堦枃傪堦暥偲偄偆偑丄乽暥乿偼懌戃偺戝偒偝偵傕巊傢傟偰偄傞丅



嵍乽憊慘乿丄塃乽塱妝捠曮乿乽峖晲捠曮乿亅暯巵偺擔憊杅堈傗姍憅偺宱嵪丄姩崌杅堈摍偺愢柧偱偼寚偐偣側偄丅偁傞掱搙偺枃悢偱丄宱嵪偺敪揥傪報徾偯偗偨偄丅乽堦曊忋恖奊揱乿偵傕偁傞傛偆偵丄幚嵺偵偼丄恖乆偼昍偵捠偟偨忬懺偱帩偪曕偒巗偱戙壙傪巟暐偭偨丅乽巗乿偼乽柍墢乿偺嬻娫偱丄尦偺帩偪庡偐傜傕偺傪乽柍墢乿乽柍庡乿偺忬懺偵偡傞偙偲偑丄乽巟暐偆乿偺尨媊偲峫偊傜傟傞丅側偍丄幚嵺偺弌搚忬懺偱偼丄堦嵎偟昐枃偱偼側偔丄96枃偺曽偑懡偄丅


 嵍乽廐揷嶚堦暘嬧乿
嵍乽廐揷嶚堦暘嬧乿拞乽峛廈業堦椉嬥乿乮暋惢丒奼戝乯亅愴崙帪戙丄奺愴崙戝柤偼愊嬌揑偵嬥嬧嶳偺奐敪傪峴偭偨丅怣尯偑峴偭偨偺偼乽峛廈棳乿偲屇偽傟傞丄岯摴偲捠婥岴傪暯峴偵嶌傝側偑傜嵦孈偡傞傕偺偱偁偭偨丅搚栘媄弍偱偺怣尯掔偼柤崅偄丅
塃乽宑挿戝敾嬥懠乿乮暋惢乯



 塃偐傜乽斔嶥乿乮捗寉斔丒慘屲暥栚乯乽暷愗庤乿乽揤曐捠曮乿乽棶媴捠曮乿
塃偐傜乽斔嶥乿乮捗寉斔丒慘屲暥栚乯乽暷愗庤乿乽揤曐捠曮乿乽棶媴捠曮乿乽峕屗帪戙偺壿暭乿亅奺壿暭偺戝偒偝偵拲栚丅嵍懁偵宑挿彫敾偲挌嬧丄擇暘嬥丄堦暘嬧丄姲塱捠曮丅擇楍栚偺嵍抂丄嵟屻偺彫敾偱偁傞枊枛偺乽枩墑彫敾乿偑偳傫側偵彫偝偐偭偨偐偼丄偡偖塃椬偺乽宑挿彫敾乿偲斾妑偟偰弶傔偰暘偐傞丅側偍丄偦偺塃椬偵偁傞偺偼揤曐屲椉敾嬥丅夋柺拞墰偺乽宑挿戝敾乿偺塃椬偼丄揷徖堄師偑拻憿傪柦偠偨乽撿鑐擇庨敿嬧乿丅偙傟8枃偱彫敾堦枃偲岎姺偝偣丄峕屗偺嬥尛偄偲忋曽偺嬧尛偄偺夝徚傪慱偭偨傕偺偱偁偭偨丅婎杮揑側壿暭椶偼庼嬈偱巊偄偨偄丅



 嵍乽姲塱捠曮巐暥慘亅擇廫堦攇丒廫堦攇乿乮昞棤乯愨懳揑側壿暭検晄懌傪曗偆偨傔丄揷徖堄師偑拻憿偝偣偨傕偺丅摵晄懌偺偨傔偵恀鐹惢偱偁偭偨丅嫟偵儌僨儖偲偝傟偨偺偼丄塃偺惔挬慘乮峃鄦捠曮丒璐惓捠曮乯偱偁偭偨丅
嵍乽姲塱捠曮巐暥慘亅擇廫堦攇丒廫堦攇乿乮昞棤乯愨懳揑側壿暭検晄懌傪曗偆偨傔丄揷徖堄師偑拻憿偝偣偨傕偺丅摵晄懌偺偨傔偵恀鐹惢偱偁偭偨丅嫟偵儌僨儖偲偝傟偨偺偼丄塃偺惔挬慘乮峃鄦捠曮丒璐惓捠曮乯偱偁偭偨丅
 乽峕屗婜彫敾堦棗乿乮昞棤乯亅宑挿彫敾偐傜枩墑彫敾傑偱偺戝偒偝丄検栚乮廳偝乯丄昳埵傪妋擣偱偒傞丅壓晘偒偵側偭偰偄傞偑偦偺棙梡壙抣偼崅偔丄峕屗帪戙慡斒偺彫敾夵拻偺楌巎偑暘偐傞丅嵟弶偺壿暭夵拻偼尦榎偺壃尨廳廏偵傛傞傕偺偩偑丄尦榎擭娫偦偺傕偺偑宱嵪偺惉挿婜偵偁偨傝丄壿暭偺愨懳検傪昁梫偲偟偰偄偨丅屻偵敀愇偼丄廳廏偺壿暭夵拻傪旕擄偟丄惓摽丄嫕曐偲嬥壿偺幙傪岦忋偝偣偨偑丄捠壿検偺晄懌偐傜怺崗側僨僼儗傪彽偒丄媑廆偺尦暥偺夵拻偱彫敾偺昳埵傪65亾丄挌嬧偺昳埵傪46僷乕僙儞僩偵棊偲偟揔搙偺僀儞僼儗岠壥傪傕偨傜偟丄埲屻丄尦暥婜偺嬥嬧壿偼80擭娫偺挿婜偵傢偨偭偰埨掕偡傞偙偲偵側偭偨丅
乽峕屗婜彫敾堦棗乿乮昞棤乯亅宑挿彫敾偐傜枩墑彫敾傑偱偺戝偒偝丄検栚乮廳偝乯丄昳埵傪妋擣偱偒傞丅壓晘偒偵側偭偰偄傞偑偦偺棙梡壙抣偼崅偔丄峕屗帪戙慡斒偺彫敾夵拻偺楌巎偑暘偐傞丅嵟弶偺壿暭夵拻偼尦榎偺壃尨廳廏偵傛傞傕偺偩偑丄尦榎擭娫偦偺傕偺偑宱嵪偺惉挿婜偵偁偨傝丄壿暭偺愨懳検傪昁梫偲偟偰偄偨丅屻偵敀愇偼丄廳廏偺壿暭夵拻傪旕擄偟丄惓摽丄嫕曐偲嬥壿偺幙傪岦忋偝偣偨偑丄捠壿検偺晄懌偐傜怺崗側僨僼儗傪彽偒丄媑廆偺尦暥偺夵拻偱彫敾偺昳埵傪65亾丄挌嬧偺昳埵傪46僷乕僙儞僩偵棊偲偟揔搙偺僀儞僼儗岠壥傪傕偨傜偟丄埲屻丄尦暥婜偺嬥嬧壿偼80擭娫偺挿婜偵傢偨偭偰埨掕偡傞偙偲偵側偭偨丅



 嵍乽挿嶈杅堈慘乿亅挿嶈杅堈偱偺桝弌梡偵拻憿偝傟偨傕偺丅拞乽敓娰捠曮乿塃乽棶媴捠曮乿亅奐崙屻偺杅堈寛嵪梡偵拻憿偝傟偨傕偺丅
嵍乽挿嶈杅堈慘乿亅挿嶈杅堈偱偺桝弌梡偵拻憿偝傟偨傕偺丅拞乽敓娰捠曮乿塃乽棶媴捠曮乿亅奐崙屻偺杅堈寛嵪梡偵拻憿偝傟偨傕偺丅塃乽儊僉僔僐8儕傾儖嬧壿乿乽揤曐堦暘嬧乿乽埨惌堦暘嬧乿枊枛偵丄擔杮偵帩偪崬傑傟丄埨惌彫敾摍偲岎姺偝傟嬥偺戝検棳弌傪傕偨傜偟偨嬧壿丅


 乽懢惌姱嶥乿偲乽柉晹徣嶥乿亅嬥偺側偐偭偨柧帯怴惌晎偼丄偙偆偟偨晄姺巻暭傪棓敪偟丄屻偺僀儞僼儗偺尨場傪嶌偭偨丅偦傟偵偟偰傕丄懢惌姱嶥傗柉晹徣嶥偼堄奜偵彫偝偄丅
乽懢惌姱嶥乿偲乽柉晹徣嶥乿亅嬥偺側偐偭偨柧帯怴惌晎偼丄偙偆偟偨晄姺巻暭傪棓敪偟丄屻偺僀儞僼儗偺尨場傪嶌偭偨丅偦傟偵偟偰傕丄懢惌姱嶥傗柉晹徣嶥偼堄奜偵彫偝偄丅乽柧帯捠曮廫慘嶥乿亅昞丒棤
乽媽堦墌嬧壿乿乮柧帯3擭暋惢乯偲乽怴堦墌嬧壿乿乮柧帯30擭乯
夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝偟偰尒傞偙偲偑弌棃傑偡丅

 嵍偐傜乽堦墌嬧壿乿乽擇廫慘嬧壿乿乽乽廫慘嬧壿乿乽屲慘嬧壿乿乽堦慘摵壿乿乽敿慘摵壿乿乽堦椥摵壿乿丅塃乽屲廫慘嬧壿乿亅柧帯37擭丅
嵍偐傜乽堦墌嬧壿乿乽擇廫慘嬧壿乿乽乽廫慘嬧壿乿乽屲慘嬧壿乿乽堦慘摵壿乿乽敿慘摵壿乿乽堦椥摵壿乿丅塃乽屲廫慘嬧壿乿亅柧帯37擭丅柧帯6擭偵敪峴偝傟偨堦慘摵壿偼丄偦偺戝偒偝偲怓嬶崌偐傜摉帪傛偔嬥壿偲娫堘傢傟偨偲傕偄傢傟傞丅側偍丄壿暭偺棤偺棾偺挙嬥偼丄峕屗偺搧憰嬶傪惢嶌偟偰偄偨壛擺壞梇偲偦偺岺朳偺怑恖払偱偁偭偨偑丄挙傝忋偑偭偨崗報傪尒偨偍屬偄奜崙恖偼偦偺鉱枾偝偵愩傪姫偄偨偲偄傢傟傞丅

 乽擔杮嵟弶偺嬧橻姺寯乿偲乽崙棫嬧峴寯乿乮嫟偵暋惢乯亅巻暭偺戝偒偝偵拲栚偝偣偨偄丅夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝偟偰尒傞偙偲偑弌棃傑偡丅
乽擔杮嵟弶偺嬧橻姺寯乿偲乽崙棫嬧峴寯乿乮嫟偵暋惢乯亅巻暭偺戝偒偝偵拲栚偝偣偨偄丅夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝偟偰尒傞偙偲偑弌棃傑偡丅塃徍榓5擭偺乽嬥橻姺寯乮悰尨摴恀乯乿偲晄姺巻暭丄摨擭偺乽嬥橻姺寯乮榓婥惔杻楥乯乿
嬥橻姺寯偼丄乽崯寯堷姺偵嬥壿仜殺憡搉壜怽岓乿偺昞婰偑偁傝丄晄姺巻暭偵偼偦偺暥帤偼側偄丅嬥夝嬛偵摜傒愗偭偨嵍偺巻暭偼庼嬈偱惀旕巊偄偨偄偲偙傠丅夝嬛偺梻擭偵偼捈偪嵞嬛巭偺慬抲偑偲傜傟偨偙偲帵偡偵偼丄摨堦偺巻暭傪梡偄偨偄丅
乽枮揝姅寯乿乽搶梞戱怋姅幃夛幮姅寯乿乽挋拁嵚尃乿



乽巻暭偵昤偐傟偨楌巎忋偺恖暔払乿






忋嵍偐傜晲撪廻擧丒崅嫶惀惔丒斅奯戅彆丒埳摗攷暥丅擔杮嵟弶偺徰憸擖傝巻暭偼乽恄媨峜岪乿偱偁偭偨偑丄忋偺晲撪廻擧摨條丄僪僀僣恖僉僆僜乕僱偺庤偵側傞傕偺偱偁偭偨丅

 嵍乽戜榩嬧峴寯乿亅嬥梈嫲峇偺愢柧偱丄楅栘彜揦偲偺娭楢偱巊梡丅
嵍乽戜榩嬧峴寯乿亅嬥梈嫲峇偺愢柧偱丄楅栘彜揦偲偺娭楢偱巊梡丅塃乽徹巻晅廫墌寯乿偲乽怴墌乿丅敪峴偑娫偵崌傢偢媽廫墌寯偺塃忋偵徹巻傪揬傝晅偗偨傕偺丅側偍丄壓偺怴墌偼僨僓僀儞偑廫帤偵尒偊偨偙偲偐傜晄恖婥偱偁偭偨丅愴屻偺宱嵪崿棎傇傝偑塎傢傟傞丅
乽奺庬孯昜丒崙嵚乿



 嵍偐傜乽擔業愴憟孯昜乿乽巟撨帠曄崙嵚乿乽曬崙嵚尃乿乮徍榓15擭丒17擭乯乽戝搶垷愴憟妱堷崙嵚乿亅徰憸偵偼摗尨姍懌偑梡偄傜傟偰偄傞丅
嵍偐傜乽擔業愴憟孯昜乿乽巟撨帠曄崙嵚乿乽曬崙嵚尃乿乮徍榓15擭丒17擭乯乽戝搶垷愴憟妱堷崙嵚乿亅徰憸偵偼摗尨姍懌偑梡偄傜傟偰偄傞丅
 嵍乽枮廈廳岺嬈姅幃夛幮姅寯乿亅埣愳媊偺憂愝偵傛傞丅壓偺枮廈揹嬈姅幃夛幮偼摨幮偺巕夛幮偱偁偭偨丅丅
嵍乽枮廈廳岺嬈姅幃夛幮姅寯乿亅埣愳媊偺憂愝偵傛傞丅壓偺枮廈揹嬈姅幃夛幮偼摨幮偺巕夛幮偱偁偭偨丅丅塃乽枮廈揹嬈姅幃夛幮姅寯乿
擔杮偺怉柉抧宱塩偱儁僀偟偨偺偼戜榩偺傒偱丄枮廈傗挬慛偱偼帩偪弌偟偑懡偐偭偨丅




嵍乽擔壺帠曄孯昜乿
塃乽戝搶垷愴憟孯昜乿
奺抧堟偱巊傢傟偨孯昜傪崟斅偄偭傁偄偵揬傝晅偗偰偦偺愴慄偺峀偑傝傪帇妎偵慽偊傞偙偲傕弌棃傞丅
杮暔偑擖庤偱偒側偄応崌偼丄乽擔杮壿暭僇僞儘僌乿乮擔杮壿暭彜嫤摨慻崌曇乯宖嵹偺孯昜傪棤昞丄幚悺戝偵奼戝僐僺乕偟揬傝崌傢偣偰巊偆偙偲傕弌棃傞丅

 嵍乽愴帪壓偺傾儖儈壿乿亅忋抜嵍偐傜廫慘乮徍榓15擭乯丄廫慘乮徍榓19擭乯丄屲慘乮徍榓侾15擭乯丅壓抜嵍偐傜慡偰堦慘乮徍榓14丄15丄16丄17丄18丄19擭乯偩偑丄師戞偵彫偝偔丄枖敄偔側偭偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅
嵍乽愴帪壓偺傾儖儈壿乿亅忋抜嵍偐傜廫慘乮徍榓15擭乯丄廫慘乮徍榓19擭乯丄屲慘乮徍榓侾15擭乯丅壓抜嵍偐傜慡偰堦慘乮徍榓14丄15丄16丄17丄18丄19擭乯偩偑丄師戞偵彫偝偔丄枖敄偔側偭偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅丂 屆慘偼嵟嬤傛偆傗偔廂廤偟巒傔偨傕偺偩偑丄宍傗戝偒偝丒僨僓僀儞傪幚姶偱偒傞揰偱丄庼嬈偱偺妶梡偼岠壥揑偱偁傞丅搨偺乽奐尦捠曮乿偲乽榓摨奐噍乿丄乽宑挿彫敾乿偲枊枛偺乽枩墑彫敾乿摍偺斾妑傗乽彫敾堦枃偼堦暘嬧傗擇庨嬧偱偼壗枃暘偐乿摍偺栤偄偵偼寚偐偣側偄戙暔偱偁傞丅栜榑丄傕偺偵傛偭偰悢廫枩偐傜悢昐枩墌傕偡傞屆慘傕偁傞偑丄庼嬈偱偼杮暔丒暋惢傪庢傝崿偤偰偺棙梡偱廫暘偱偁傞丅乽憊慘乿乽塱妝捠曮乿乽峖晲捠曮乿乽姲塱捠曮乿乽揤曐捠曮乿摍偼杮暔偱傕斾妑揑埨偔庤偵擖傟傞偙偲偑弌棃傞丅偦偆偄偊偽丄乽晉杮慘乿偺柾憿昳傕偁偭偨偭偗丅
丂 枖丄巻暭偵報嶞偝傟偰偄傞徰憸偵拲栚偟偰棙梡偡傞応崌傕偁傞丅乽摗尨姍懌乿乮戝搶垷愴憟崙嵚乯丄乽榓婥惔杻楥乿乮媽廍墌嶥乯丄乽悰尨摴恀乿乮媽屲墌嶥乯丄乽擇媨懜摽乿乮媽堦墌嶥乯丄乽崅嫶惀惔乿乮媽屲廍墌乯丄乽惞摽懢巕乿乮媽堦枩墌嶥乯乮巚偄愗偭偰杮暔傪惗搆偵夞棗乯摍乆丅乽埳摗攷暥乿乮媽愮墌嶥乯丒乽戝孏廳怣乿丒乽斅奯戅彆乿摍偼丄偦傟偧傟偺応柺偱偺棙梡偑壜擻丅
丂 揷徖堄師偑敪峴偟偨乽姲塱捠曮巐暥慘乿乽撿鑐擇庨嬧乿偼捠壿検偦偺傕偺偺憹戝傪栚巜偟偨傕偺丄乽挿嶈杅堈慘乿傗乽敓娰捠曮乿偼杅堈寛嵪偺偨傔偵梡偄傜傟偨傕偺丄枖丄乽斔嶥乿傗乽愬戜捠曮乿摍偼斔偺嵿惌擄偺壗傛傝偺徹嫆偲偟偰巊偊傞丅柧帯弶婜偺乽懢惌姱嶥乿乽柉晹徣嶥乿偼埲奜偵彫偝偔丄乽崙棫嬧峴寯乿偵偼昁偢乽戞仜仜崙棫嬧峴寯乿偲報嶞偝傟丄嵟弶偺乽嬧橻姺寯乿昐墌嶥偺戝偒偝偵偼暵岥偟偰偟傑偆丅徍榓2擭偺乽棤敀昐墌寯乿偼嬥梈嫲峇偱丄徍榓5擭偺乽橻姺廍墌寯乿偼嬥夝嬛偱丄奺庬孯昜偼擔惔乣懢暯梞愴憟偱偺愢柧偱偼寚偐偣側偄屆慘偱偁傞丅
乮弔廐愴崙帪戙偺搧慘丄壿晍丄媋旲慘丄娍偺敿椉慘丄懛暥傗逋悽奙傪崗傫偩拞壺柉崙堦墌嬧丄僪僀僣偺儗儞僥儞儅儖僋傗僀儞僼儗巻暭丄懡柉懓崙壠偱偁傞偙偲偑暘偐傞僀儞僪傗拞崙偺巻暭丄僄儕僓儀僗彈墹偺崄峘僐僀儞傗摨僇僫僟巻暭丄棝丂弚恇偲婽峛慏傪僨僓僀儞偟偨娯崙巻暭摍丄楌巎忋偺恖暔偑報嶞丒崗傑傟偨奺崙巻暭丒僐僀儞側偳丄屆慘偼愗庤摨條悽奅巎傗抧棟偱偺妶梡斖埻傕峀偔丄崱屻嫟丄廂廤偵椡傪拲偄偱偄偒偨偄丅乯
儈僯儈僯擔杮壿暭巎
丂屆慘丒巻暭偼嬤偔偺僐僀儞僔儑僢僾傗丄僨僷乕僩偱偺懄攧夛摍偱斾妑揑擖庤偟傗偡偄丅埲壓丄屆慘丒巻暭偵娭偡傞庼嬈偱巊偊傞楌巎揑側榖戣傪捛偭偰傒傛偆丅側偍丄偙偺峞偼丄搶栰帯擵挊乽壿暭偺擔杮巎乿乮挬擔慖彂乯丄HP丄擔杮嬧峴嬥梈尋媶強乽壿暭攷暔娰乿偺乽壿暭偺嶶曕摴戞堦榖乣戞屲廫巐榖乿丄摨乽嬥梈尋媶姫摢僄僢僙乕僔儕乕僘乿丄嶰栘棽嶰乽搉棃慄偺幮夛巎乿乮拞岞怴彂乯摍偵懡偔埶嫆偟偨偙偲傪梊傔柧婰偟偰偍偔丅枖丄壿暭偺僇儔乕恾斉丄尰嵼偺昡壙妟摍傪抦傞偨傔偵偼丄枅擭姧峴偝傟偰偄傞乽擔杮壿暭僇僞儘僌乿乮擔杮壿暭彜嫤摨慻崌乯偑桳梡偱偁傞丅摨彂姫枛偵偼丄屆慘丒巻暭偺捠斕夛幮偺峀崘偑宖嵹偝傟偰偄傞丅
墌宍曽岴偺堄枴丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂拞崙嵟弶偺壿暭偱偁傞丄弔廐愴崙帪戙偺搧慘傗壿晍摍偺惵摵壿暭偼丄偦偺撈摿側宍偱壿暭偱偁傞偙偲傪廃埻偵帵偟偨偑丄壗偲偄偭偰傕帩偪塣傃傗惍棟偵搒崌偑埆偐偭偨丅偦偙偱丄恅偺巒峜掗偑庢傝埖偄偺梕堈側丄墌宍偺宍偵摑堦偟偨偺偑巒傑傝丅
丂怶偺楧朖偼乽慘恄榑乿偺拞偱丄墌偼揤傪丄曽宍偺岴偼抧傪徾挜偡傞傕偺偲弎傋偰偄傞偑丄曽岴偵偼傛傝嬶懱揑側昁慠惈偑偁偭偨丅偦傟偼曽岴偵朹傪捠偟偰儘僋儘偑偗傪偟丄拻憿偺嵺偵偱偒傞僶儕傪庢傝彍偔堊偱偁偭偨丅
榓摨奐噍丂丂丂丂丂
丂暯惉嬨擭偵敪尒偝傟偨晉杮慘偵傛偭偰丄擔杮嵟弶偺壿暭偲偄偆抧埵傪嫼偐偝傟偨榓摨奐噍偱偁偭偨偑丄晉杮慘偑丄杺傛偗傗彽暉偺墋彑慘偱偁偭偨乮曽岴偺嵍塃偵偁傞幍偮偺揰偼丄懢梲丄寧丄栘丄壩丄搚丄嬥丄悈傪昞偡偲偝傟傞乯偺偵懳偟丄弶傔偐傜壿暭偲偟偰偺棳捠傪栚巜偟偨榓摨奐噍偙偦丄傗偼傝擔杮嵟弶偺壿暭偱偁偭偨丅榓摨奐噍偼丄晲憼崙偐傜榓摵偑敪尒偝傟偨偺傪偒偭偐偗偲偟偰拻憿偝傟偨偑丄摵慘敪峴偵愭棫偪嬧慘偑敪峴偝偰偄傞偺偼丄榓摵乮帺慠摵乯偩偗偱偼摵慘傪戝検敪峴偱偒側偐偭偨帠忣偵傛傞丅幚偼嬧慘偼丄摵慘偺戝検敪峴偵傆偝傢偟偄帺慠摵偺敪尒傑偱偺偮側偓偱偟偐側偐偭偨丅乮嬧慘偼屻偵攑巭偝傟偰偄傞乯
丂廃抦偺捠傝丄榓摨奐噍偺儌僨儖偲偝傟偨偺偼丄搨偺奐尦捠曮偱偁傞偑丄偙傟偼乽奐捠尦曮乿偲塃夞傝偱撉傓偺偑惓偟偄丅堦斒偵乽丒丒尦曮乿偺応崌偼塃夞傝偱丄乽丒丒捠曮乿偺応崌偼忋壓嵍塃偱撉傓丅
丂枖丄奐尦捠曮偼丄変偑崙偺搙検峵偺婎慴傪側偟丄栨偲偄偆廳検扨埵偼丄奐尦捠曮侾枃傪侾暥栚偲偄偭偨偙偲偐傜棃偨尵梩偱丄懌戃偺戝偒偝傪壗暥偲偄偆偺傕丄奐尦捠曮傪墶偵暲傋偨挿偝偐傜巒傑偭偨偲傕偄傢傟傞丅
峜挬廫擇慘
榓摨奐噍偐傜暯埨帪戙偺姡尦戝曮傑偱丄惌晎偵傛偭偰敪峴偝傟偨峜挬廫擇慘偼丄尨椏偺摵晄懌偐傜彊乆偵昳埵偑棊偪丄嵟屻偺姡尦戝曮偵帄偭偰偼丄杦偳墧慘偱偁偭偨丅怴慘偼媽慘偺10攞偱偺岎姺偑掕傔傜傟丄尨椏偺摵偼丄夞廂偝傟偨媽慘偵媮傔傜傟偨丅塱墑尦擭乮987擭乯丄慘壿偺棙梡掆巭偑惌晎偵傛傝敪偣傜傟埲屻丄擔杮偼憊慘傪棙梡偡傞12悽婭屻敿傑偱丄暷傗對晍偑壿暭偺戙傢傝偲偟偰梡偄傜傟偨丅
丂屆偔偐傜堫偑丄岎姺庤抜偲偟偰梡偄傜傟偰偄偨偙偲偼丄堫傪尦乆乽僱乿偲敪壒偟偰偄偨偙偲偐傜傕悇應偝傟傞丅乽抣抜乿偼堫偺乽僱乿偵桼棃偡傞尵梩偱偁偭偨丅
搶偺僐僀儞丄惣偺僐僀儞
丂拞崙傗擔杮偺屆慘偼丄拻宆偵嬥懏傪棳偟崬傫偱拻憿偝傟偨傕偺偱偁偭偨偑丄僊儕僔傾丄儘乕儅丄惣傾僕傾偺偦傟偼丄堦掕検偺嬥懏夠傪昞棤偺宆偺娫偵嫴傒丄弖娫揑偵戝偒側椡傪壛偊偰暥條傪懪崗偟偰憿傜傟偨乮抌憿乯丅場傒偵丄惣梞偱寠偁偒僐僀儞偑彮側偄偺偼丄懪埑偵傛傞寠偁偗偑柺搢側嶌嬈偱偁偭偨偙偲偵傛傞丅
丂偙偺堘偄偼丄堦掕昳埵偺壿暭偑懜廳偝傟丄挿婜偵傢偨偭偰敪峴偝傟傞偙偲偑懡偐偭偨惣傾僕傾埲惣偵懳偟丄拞崙偱偼惌帯尃椡偵傛偭偰壿暭偺幙偑嵍塃偝傟偑偪偱偁偭偨帠忣偵傛傞偑丄惣偺僐僀儞偑壙抣偺広搙傗杅堈壿暭偲偟偰偺栶妱傪壥偨偟偰偄偨偺偵懳偟丄搶偺偦傟偼崙壠偑嶌傝弌偟偨巟暐偄庤宍偲偟偰偺栶妱傪壥偨偟偰偄偨偲偄偆堘偄偵傕娭楢偑偁傞丅枖丄悽奅揑偵尒偰丄嬥壿傛傝傕嬧壿偺曽偑僐僀儞偺楌巎偵憗偔巔傪尰偟偨偺偼丄嵒嬥偲偟偰梕堈偵庢傝弌偣偨嬥傛傝傕丄暔棟揑丒壔妛揑憖嶌傪壛偊側偗傟偽側偐側偐庢傝弌偣側偐偭偨嬧偺曽偑壙抣偑崅偐偭偨偙偲偵傛傞丅丂
憊丂慘
丂暯埨丄姍憅丄幒挰帪戙偼丄惌尃偑惼庛偱慡崙偱棳捠偡傞摑堦壿暭傪拻憿偱偒側偐偭偨丅偙偙偵拞崙偐傜偺搉棃慘偑搊応偡傞丅幚偼搉棃慘偺戝敿偼杒憊慘偱偁偭偨丅廃抦偺傛偆偵丄暯惔惙偑悇恑偟偨擔憊杅堈偱丄擔杮偼墱廈嶻偺嬥傪桝弌偟丄拞崙偐傜戝検偺憊慘乮杒憊慘乯傪桝擖偟偨丅憊慘偺棳捠偵偼丄戝椫揷偺攽偺抸峘傗楡壺墹堾丄尩搰恄幮偺憿塩摍丄惔惙偑峴偭偨戝宆寶愝僾儘僕僃僋僩偑偒偭偐偗偲側偭偨丅帯彸嶰擭乮1179擭乯榋寧偺乽昐楤彺乿偵偼丄乽揤壓忋壓昦傒擸傓丅偙傟傪慘昦偲崋偡丅乿偲婰偝傟丄偦偺棳捠傇傝偑塎傢傟傞丅
丂壗偟傠丄憊慘乮戝敿偑杒憊慘乯偼丄昳埵丄検栚乮廳偝乯丄宍忬偺忋偱嬒幙偱偁偭偨偺偵壛偊丄偦偺拻憿崅偼寘奜傟偵戝検偱偁偭偨丅尦朙擭娫乮1078乣85擭乯偩偗偱傕丄枅擭600枩娧乮60壄枃乯偵払偟丄傾僼儕僇搶奀娸丄惣傾僕傾丄僀儞僪丄搶撿傾僕傾傑偱偦偺棳捠斖埻偼奼戝偟偰偄偨丅崙撪偱偼丄擭峷慘擺壔偺斾棪偼丄姍憅枛偱栺敿暘丄幒挰偺弶婜偱偼栺8妱偵傕払偟偰偄偨丅丂
塱妝捠曮
丂 柧偺椙幙側摵慘偱塱棃慘偼搉棃摉弶偐傜峀偔棳捠偟偨偐偺傛偆偵巚傢傟傞偑丄幚偼塱妝慘偼嵟弶偼寵傢傟偰偄偨慘壿偱偁偭偨丅偦傟偼拻憿検偵偍偄偰杒憊慘偵偐側傢側偐偭偨偙偲偑堦斣戝偒側尨場偱偁偭偨偑丄柺敀偄偙偲偵丄柧崙撪偱偼婛偵巻暭偑庡棳傪愯傔丄柧慘偺巊梡偼婖旔偝傟偰偍傝丄尦乆丄塱妝捠曮偼擔杮岦偗偺桝弌昳偲偄偆惈奿偑偁偭偨丅塱妝捠曮偺彂偼丄搶栰帯擵巵偺慜宖彂偵傛傟偽丄嵟弶偺尛柧慏偵摨忔偟偨屲嶳憁丄拠曽拞惓偺庤偵側傞傕偺偱偼偲悇應偝傟偰偄傞偑丄偦偆偟偨帠忣傪峫椂偡傞偲丄幚嵺偵偁傝摼偨偙偲側偺偐傕偟傟側偄丅塱妝捠曮偼丄搨丒憊摍偺屆慘傪懜廳偟偰偄偨惣擔杮偱摿偵婖旔偝傟丄寢壥揑偵搶擔杮偵戝検偵棳傟崬傒婎幉捠壿偲偟偰偺嵗傪愯傔偰備偔丅
丂乽塱姩掕乿偲偄偊偽丄塱妝捠曮1枃偵懳偟鑋慘4枃偺岎姺斾棪傪巜偟丄怐揷怣挿傗恀揷岾懞偑丄塱妝捠曮傪婙報傗壠栦丄搧寱偺捳偵梡偄傞側偳丄偦偺幮夛傊偺怹摟傇傝偑憐憸偝傟傞偑丄偁偺廏媑偼丄塱妝捠曮偲柫懪偭偨嬥慘丄嬧慘偺拻憿傪峴偭偰偄傞偺偱偁傞丅
巹拻慘丒鑋慘
丂 偦偺屻丄拞崙偱偼摵壿晄懌偑怺崗壔偟丄塱嫕4擭丄偮偄偵偦偺桝弌偑嬛巭偝傟偨丅偙偆偟偨拞偱幒挰枊晎偼丄挬慛丄埨撿丄棶媴偐傜傕慘壿傪桝擖偡傞堦曽丄拞崙偺巹拻慘傗崙撪偺巹拻慘偺棳捠傕擣傔偞傞傪摼側偐偭偨丅昳幙傗宍丒戝偒偝傕嶨懡側慘壿偑摨帪偵棳捠偟偨偙偲偐傜丄摉慠偺傛偆偵埆慘傪婖旔偡傞愶慘峴堊偑悘強偱尒傜傟丄枊晎傗奺愴崙戝柤偼孞傝曉偟愶慘椷傪敪偟丄偦偺岎姺斾棪傪掕傔側偑傜丄墌妸側彜庢堷傪曐徹偟傛偆偲偟偨丅幚偼丄愶慘峴堊傕17悽婭屻敿偐傜堦揮偟偰摵偺桝擖崙偵側偭偰偄偨拞崙偐傜傕偨傜偝傟偨尰徾偱偁偭偨丅偙偺崰丄杮暔偺壿暭偐傜捈愙揱幨偟偨拻幨慘偺悢偼懡偔丄擔嬧壿暭攷暔娰強憼偺傕偺偩偗偱傕丄64庬椶偵傕偺傏傞乮戙昞揑側傕偺偼搰捗椞撪偱拻憿偝傟偨乽壛帯栘慘乿乯丅枖丄乽鑋堦暥丄暐傢偹偊乿偺乽鑋乿偼榓惢娍帤偱丄尦乆丄懪偪傂傜傔乮彫宆偺慘傪扏偄偰暯偨偔堦斒慘暲偵奼戝偟偨傕偺乯偲嬫暿偡傞梡岅偱偁偭偨偑丄寚懝慘傗妱傟慘傪彍偔慹埆慘堦斒傪巜偟丄乽廳偹崌傢偡偲價僞價僞壒偑偡傞乿傕偟偔偼乽摵慘偺昞柺偵偁傞拻暥帤偑儊僞儊僞偵側偭偰偄傞乿偙偲偐傜柤晅偗傜傟偨傕偺偱偁傞丅暿偵嫗慘乮僉儞僙儞乯偲傕屇偽傟偨丅
丂 庼嬈偱偼丄杮暔偺峖晲捠曮偲偦偺巹拻慘傪僙僢僩偱帵偟丄偦偺堘偄乮乽峖乿偺偝傫偢偄偺偼偹偐偨乯偵婥偯偐偣偰偄傞偑丄悢庬椶偺塱妝捠曮傪帩偪崬傒丄偦偺懡條惈偵婥偯偐偣偨偄丅丂強偱丄偙偆偟偨巹拻慘偺嵽椏偼偳偙偐傜傕偨傜偝傟偨傕偺偩傠偆丅偦傟偼屻婜峜挬慘傗丄妱傟丒寚偗偺偁傞搉棃慘傪梟夝偟偰拻憿偝傟偨偲巚傢傟傞偑丄巹拻慘偼嵟弶偐傜堦枃偢偮棙梡偝傟偢丄100枃扨埵偱昍偱妵傜傟偨慘嵎偟偺拞偵悢枃崿偤偰梡偄傜傟偨丅
拞悽偺嬥梈丒彜庢堷
丂 姍憅帪戙偺嶰嵵巗丄幒挰帪戙偺榋嵵巗偲偄偊偽丄嫵壢彂偵傕搊応偡傞婎杮揑側梡岅偺堦偮偩偑丄屆戙埲棃丄巗偑棫偮応強偼丄壨尨丄愳偺拞廈丄奀昹丄嶁偺搑拞摍偱偁偭偨丅
丂埲壓丄栐栰慞旻乽楌巎傪峫偊傞僸儞僩乿乮怴挭慖彂乯偵懡偔埶傝側偑傜摉帪偺彜嬈丄嬥梈娭學偺榖戣傪婔偮偐徯夘偟偰偍偔丅
丂 愭偢丄側偤丄巗偑棫偮応強偑慜婰偺応強側偺偱偁傠偆偐丠偦傟偼丄偳偺応強傕丄惞偲懎偺嫬奅椞堟偱丄尦乆偺強桳娭學偐傜墢偼愗傟傞柍墢偺嬻娫偱偁偭偨偐傜側偺偱偁傞丅暯埨帪戙偵擑偑棫偭偨応強偵巗傪棫偰傞廗姷偑偁偭偨偑丄偙傟傕丄揤偺悽奅偲恖娫偺悽奅偲偺嫬奅偱偁偭偨偐傜偱丄柍墢偺応強偵傕偺傪搳偘擖傟傞偙偲偵傛偭偰弶傔偰恖娫偼傕偺傪彜昳壔偡傞偙偲偑弌棃偨丅偐偮偰壧奯偑巗偱峴傢傟偰偄偨傛偆偵偦偙偱偼帺桼側惈岎徛傕峴傢傟偰偄偨偺偱偁傞丅巗偱乽巟暐偆乿峴堊偼丄乽釶偆乿偐傜棃偨尵梩偱偁偭偨丅乽愗傞乿乽棊偲偡乿峴堊偵傛偭偰丄扤偺暔偱傕側偄柍庡暔乮柍墢乯偲側傝丄傕偺偲偟偰帺桼偵攧攦偱偒偨偺偱偁傞丅儈儗乕偺乽棊偪曚廍偄乿偼丄傑偝偵偦偺偙偲傪帵偡楌巎揑側奊夋側偺偱偁傞丅
丂棙懅傪庢傞峴堊偺巒傑傝偼棩椷惂偺傕偲偱峴傢傟偰偄偨弌嫇偵慿傞丅嵟弶偵廂妌偝傟偨惞側傞弶曚傪憼偵擺傔丄梻擭丄偦傟傪庬栢偲偟偰擾柉偵戄偟晅偗丄棙懅偲偟偰栺俆妱偺堫乮棙堫乯傪挜廂偟偨乮5妱偺棙堫偼廂妌検偐傜尒傞偲偝傎偳崅偄傕偺偱偼側偐偭偨乯丅偙偺傛偆偵丄嬥梈偼摉弶丄恄暔丄暓暔傪塣梡偟偦偺曉楃偲偟偰棙懅傪恄暓偵栠偡偲偄偆宍偱敪惗偟乮悽奅揑偵嫟捠乯偨偺偱偁傞丅拞悽埲崀丄弶曚偼乽忋暘乿乽忋暘慘乿偲傕屇偽傟丄偦傟傜傪尦杮偲偟偨戄晅偑峀偔峴傢傟傞傛偆偵側偭偨偑乮偙偆偟偨峴堊傕丄弌嫇傗庁忋偲屇偽傟偰偄偨乯偦傟傜偼恄暓偺暔傪戄晅偗傞峴堊偩偭偨偺偱丄懎恖偑実傢傞偙偲偼弌棃偢丄擔媑忋暘暔偼擔媑恄恖傗塨嶳偺嶳憁偑丄枖丄孎栰忋暘慘偼孎栰恄恖傗嶳暁払偑偦傟偧傟扴摉偟偨丅屻偺丄搚憅偺戝敿偑乽嶳栧婥晽偺搚憅乿偲偐乽嶳朄巘偺搚憅乿偲屇偽傟幚嵺偵朄懱偺幰偑懡偐偭偨偺偼丄墑楋帥傪杮強偲偟偰偄偨偐傜側偺偱偁傞丅
丂13悽婭屻敿崰偐傜丄寧棙偱棙懅傪庢偭偰慘傪戄偟晅偗傞棙慘偺嬥梈偑巒傑傝丄惞側傞峴堊偩偭偨嬥梈偑悽懎壔偟偰偄偭偨丅嵟傕偦偺偙偲傪帵偡偺偑丄搚憅偑堦斒偐傜棙巕晅偱庁傝擖傟偦傟傪尨帒偲偟偰庁慘傪峴偆乽崌慘乿偱偁偭偨丅摉帪偺棙懅偼丄昐暥偵偮偒寧俆暥乣俇暥偱偙傟傪俆暥巕丄6暥巕偲屇傫偱偄偨丅偮傑傝丄慘偼巕傪嶻傓偲偲傜偊丄棙懅傪棙巕偲傕屇傫偩偺偱偁傞丅摉帪丄棙懅偼乽棙攞朄乿偱10妱傑偱偲偝傟偰偄偨偑丄幒挰帪戙偵側傞偲暋棙摍偺朶棙傪偲傞崅棙戄偟偑惙傫偵側偭偰備偒丄廃抦偺捠傝丄摽惌堦潉偺尨場偲傕側偭偰偄偭偨乮帥幮偑峴偭偨嬥梈峴堊偱偁傞釱摪慘偺応崌偼丄棙巕偼擇暥巕偱摉帪偺棙巕棪悈弨偐傜傒傟偽掅棙偱偁偭偨丅釱摪慘偼丄壝媑偺摽惌椷埲棃丄摽惌偺懳徾奜偲偝傟偰偄偨乯丅
丂尰嵼丄巊傢傟偰偄傞乽庢堷乿偵娭傢傞梡岅偵偼丄拞悽偺梡岅傗奀偵娭傢傞傕偺偵敪偡傞傕偺偑懡偄丅乽姅幃乿偺乽姅乿偼丄幮夛偺惉堳偲偟偰偺抧埵傗帒奿傪巜偟丄乽幃乿偼乽抧摢怑乿傗乽椞壠怑乿偺傛偆偵丄摼暘乮廂擖乯傪敽偆怑柋偐傜棃偨尵梩偱偁偭偨丅枖丄嵟弶偺抣抜偑寛傑傞乽婑傝偮偒乿偼丄乽恖偺椡偑媦偽側偄悽奅偐傜壗偐偑傗偭偰偔傞乿偲偄偆堄枴傪桳偟丄偐偮偰奀娸偵棳傟拝偄偨昚棳暔偼乽婑暔乿偲偟偰丄嵟弶偵堷偒婑偣偨懞偺恖乆偺傕偺偵偝傟偨偲偄偆廗姷偵婎偯偔丅偮傑傝丄嵟弶偺抣抜偑寛傑傞偺偼乽恖偺椡傪墇偊偨椡偵傛傞乿偲偄偆姶妎偑偦偺攚宨偵偁偭偨乮偪側傒偵偦偺婑暔偼帥幮偺廋棟丄憿塩旓偵偁偰傜傟傞傕偺偲偝傟偰偄偨乯丅
丂枖丄憫墍偵傗偭偰偒偨崙栶恖傗媞恖偵懳偟偰丄廤棊偺嫬偱庰嶆傪嬂墳偡傞偙偲傪乽嫙媼乿丄憫墍撪偱嶰擔娫偵傢偨偭偰庰墐傪奐偒傕偰側偡偙偲傪乽棊拝乿乮嶰擔悀乯偲尵偭偨偺偱偁傞丅枖丄弾柉嬥梈偱偁偭偨乽棅曣巕乿偼乽棅傕偟偄乿偐傜丄乽柍恠乿偼暓嫵偺乽柍恠嵿乿偐傜偦傟偧傟敪惗偟偨尵梩偱偁偭偨丅
丂 偙偺摉帪丄堦僇強偱嵟懡偺摵慘偑弌搚偟偨偺偼巙戂娰愓乮敓娰巗巙奀戂挰乯偐傜偺俁俈枩俆愮枃庛丅愘挊偱偼丄乽侾係俆俈擭偺僐僔儍儅僀儞偺棎偱娮棊偟偨嵺偵杽傔傜傟偨乿偲婰弎偟偨偑丄偦偺屻丄妛桭岺摗惔懽巵偐傜丄巙戂娰偼侾俆悽婭屻敿傑偱巊梡偝傟偰偄傞傜偟偔丄娮棊偼堦帪揑側壜擻惈傕偁傞偙偲傪偛嫵帵帓偭偨丅嵟嬤偺尋媶偱偼丄岺帠偺嵺丄戝酨俁屄偺忋晹傪攋懝偟偰敪尒偝傟偨偙偲偐傜丄幚嵺偵偼俆侽枩枃偁偭偨偺偱偼側偄偐偲偄偆愢傕偁傞丅枖丄偦偺晅嬤堦懷偼慘婽戲偲屇偽傟偰偄傞偑丄峕屗帪戙偐傜戝偵擖偭偨屆慘偑戝検偵敪尒偝傟偨偙偲偐傜慘戲偐傜揮偠偰慘婽戲偵側偭偨偲傕偝傟丄晅嬤堦懷偵偼敪尒偝傟偨壗攞偐偺検偺慘偑杽傔傜傟偰偄偨壜擻惈傕偁傞丅
丂偦傟偱偼側偤丄搚拞偵慘傪杽傔偨偺偐丠
尰嵼偺強丄旛拁慘側偺偐丄杽擺慘側偺偐偲偄偆榑憟偼寛拝偼偮偄偰偄側偄丅愭弎偺栐栰巵偺挊彂偵傛傟偽丄搚偺拞偼堎奅偱偁傝丄柍庡暔偲偝傟偨偺偱偼偲偄偆丅暯埨枛婜偐傜幒挰帪戙偵偐偗偰峀斖偵峴傢傟偨丄偍宱傪惵摵婍側偳偺梕婍偵擖傟從偒暔偵擺傔偰搚拞偵杽傔傞乽宱捤乿偺椺傕偁傝丄応強傗搚抧傪棙梡偡傞偨傔偺戙彏丄偁傞偄偼帒杮偲偟偰妶梡偡傞偨傔偵慘傪搚拞偵杽傔偨偺偱偼偲偝傟偰偄傞偑丄崱屻偺尋媶偺恑揥傪懸偪偨偄丅
愇崅惂丂丂丂丂丂丂
丂廏媑偵傛傞揤壓摑堦偺夁掱偱峴傢傟偨懢峿専抧偼丄忎検偺摑堦丄堦抧堦嶌恖偺尨懃摍丄嬤悽偺晻寶惂偺搚戜傪抸偄偨偲偄傢傟傞丅摿偵丄戝柤偺抦峴傗孯栶偺婎弨偲偝傟偨偺偑丄搚抧傪暷偺惗嶻崅偱昞偡愇崅惂偱偁偭偨丅偦傟傑偱偺妶敪側壿暭棳捠偺忬嫷傪憐婲偡傞偲丄側偤丄慘偱側偔偰暷側偺偐丄偲偄偆慺杙側媈栤偑傢偄偰偔傞丅偦傟偼丄慜弎偟偨傛偆偵丄愶慘偺峀斖壔乮摉帪丄慘壆偵壿暭壙抣偺娪掕傪埶棅偟丄寢壥揑偵庢堷旓梡偺憹戝傪懀偟偨乯傗搉棃慘偺榁媭壔摍偐傜丄慘壿偦偺傕偺偑丄壙抣婎弨偲偟偰婡擻傪戝暆偵屻戅偝偣偰偄偨帠忣偑偁偭偨偐傜偱偁傞丅壙抣偑埨掕偟丄揮攧惈偵晉傓暷偑丄慘壿偵戙傢傞傕偺偲偟偰媟岝傪梺傃丄偦偟偰偦偺偙偲偑丄廏媑偺愇崅惂偵側偭偰偄偭偨偺偱偁傞丅偙偺偙偲偼丄幒挰帪戙屻敿偐傜丄慸惻晧扴偺婎弨偑丄摵慘偐傜暷偵堏峴偟偰偄偨偙偲偲傄偭偨傝晞崌偡傞丅
撿斬杅堈偲嬧
丂丂丂丂丂丂丂丂
丂擔杮偱丄嬥丒嬧偺嶻弌偑旘桇揑偵憹戝偟偨偺偼丄16悽婭丄奃悂偒朄偲屇偽傟傞惢楤媄弍偑挬慛偐傜揱傢偭偰偐傜埲屻偺偙偲偱偁偭偨丅偙偺曽朄偼丄嬥傪娷傫偩嬧峼愇傪墧偲嫟偵梟夝崪奃偱嶌偭偨嶮偵擖傟丄墧偑崪奃偲壔崌偟偰媧廂偝傟丄偁偲偵嬥嬧偩偗偑巆傞偲偄偆夋婜揑側傕偺偱偁偭偨丅
丂摉帪乮17悽婭弶傔崰乯偺擔杮偺嬧偺嶻弌崅偼丄擭娫偱130乣170t偵払偟丄偦傟偼慡悽奅偺嶻弌崅偺係妱偵傕憡摉偟偨丅偙偺戝検偺嬧傪奀奜偵帩偪弌偟偺偑億儖僩僈儖偱偁偭偨丅尦乆丄億儖僩僈儖偼僀儞僪傗搶撿傾僕傾偺崄恏椏傪攦偄偮偗傞帒嬥傪丄杮崙偐傜塣傇偲偄偆帪娫偲儕僗僋傪旔偗傞偨傔丄摉帪丄愨戝側廀梫偑偁偭偨拞崙嶻偺惗巺傪儅僇僆偐傜擔杮傊塣傃丄偦偺嬧乮挌嬧偺宍乯傪偦偺帒嬥偵廩偰偨丅摉帪丄擔杮偐傜帩偪弌偝傟偨嬧偼擭娫20枩噑偵傕払偟偨偲偝傟傞偑丄惗巺偼柧崙撪偱堦嬕慘250暥偟偨偑丄擔杮偱偼慘5娧暥丄偮傑傝20攞偺棙塿偑栺懇偝傟偨彜昳偱偁偭偨乮1630擭戙丄惗巺偼擭30枩嬕乣40枩嬕亖栺10枩拝暘桝擖偝傟偨乯丅
丂傛偔丄撿斬杅堈偼僇僩儕僢僋偺晍嫵偲堦懱壔偟偰偄偨偲愢偐傟傞偑丄幚嵺偵億儖僩僈儖偺愰嫵巘払偼丄捈愙丄惗巺杅堈偵怺偔娭傢偭偰偍傝乮寶慜忋偱偼旕岞擣偱偁偭偨偑乯丄乽擔杮暥揟乿傪挊偟偨偁偺儘僪儕僎僗偼丄偦偺夛寁扴摉恄晝偱偁偭偨丅
奀傪搉偭偨擔杮偺嬥丒嬧丒姲塱捠曮
丂擔杮偐傜帩偪弌偝傟偨嬥偼丄僆儔儞僟搶僀儞僪夛幮摍偵傛傝丄僀儞僪傗撿梞彅崙偲偺岎堈偵偦偺傑傑梡偄傜傟丄僶僞價傾偱偼丄彫敾偼乽僋乕僶儞乿偲屇偽傟偦偺傑傑岎姺庤抜偵梡偄傜傟偨丅嬧偼丄拞崙崙撪偱偼攏掻宆偺攭検嬧壿偵拻捈偝傟丄僆儔儞僟宱桼偱僀儞僪偺儀儞僈儖抧曽傊塣傃崬傑傟丄僀儞僪捠壿儘僺傾偵巔傪曄偊偨丅偦偺屻丄挿嶈偱偺杅堈偺弅彫壔偵敽偄丄偦傟傑偱偺嬥嬧偵曄傢傝桝弌偝傟偨姲塱捠曮偼丄偦偺傑傑搶撿傾僕傾慡堟偱壿暭偺栶妱傪壥偨偟偨偑丄堦晹偼撶丒姌摍偺擔梡昳偺尨椏偵偝傟偨丅偝傜偵灗摵偺宍偱僆儔儞僟偵塣傃崬傑傟偨摵偼丄傾僟儉=僗儈僗偑乽彅崙柉偺晉乿偱拲栚偟偨傛偆偵丄傾儉僗僥儖僟儉偱偺摵巗応偱偺壙奿偺憖嶌庤抜偵梡偄傜傟偨丅
丂側偍丄擔杮偺摵偼17悽婭枛乣18悽婭弶傔崰偑僺乕僋偱擭娫俇愮僩儞嶻弌偝傟偨偑彊乆偵尭彮偟偰偄偭偨丅尦暥擭娫乮1736乣1741擭乯埲屻丄姲塱捠曮偼戝敿偑揝慘偲側傝丄揷徖偺帪偵拻憿偝傟偨姲塱捠曮巐暥慘偼乮惔挬慘偑儌僨儖乯丄垷墧24亾丒庎8亾傪娷傓恀鐹慘偵側偭偰偄偭偨丅
懡庬椶偺姲塱捠曮
丂姲塱捠曮偺拻憿偑杮奿壔偟偨偺偼姲暥敧擭乮1668擭乯丅偦傟偼嬥嬧壿偺拻憿偐傜幚偵35擭屻偺偙偲偱偁偭偨丅偱偼丄側偤丄偙傫側偵抶傟偨偺偩傠偆丅偦傟偼拞悽屻婜埲崀丄摵慘偼婛偵壙抣偺婎弨偱偼側偔側傝丄弾柉偺彫慘偲偄偆栶妱偟偐帩偨側偐偭偨偙偲偵傛傞丅枖丄姲塱捠曮偼丄嬥嬧嵗偺傛偆側悽廝偺壠偱偼側偔丄拻憿偺婓朷傪弌偟偰擣壜偝傟傟偽偳偺傛偆壠偱傕憿傟偨偙偲偐傜丄柧帯弶擭傑偱偺240擭娫偵幚偵懠庬椶乮悢昐庬乯偺姲塱捠曮偑惗傒弌偝傟偰偄偭偨丅姲暥廫擭丄姲塱捠曮埲奜偺慘壿偺捠梡偑嬛巭偝傟丄夞廂偝傟偨戝敿偺屆慘偼偦偺傑傑丄傕偟偔偼杒憊慘偵拻捈偝傟偰搶傾僕傾偵桝弌偝傟偨丅側偍丄屆慘嶨帍偱傛偔尒偐偗傞屆姲塱丄怴姲塱偲偼姲暥敧擭乮1686擭乯偺暥慘拻憿傪嫬偵嬫暿偝傟偨柤徧偱偁傞丅
峕屗偺僀儞僼儗丒僨僼儗
丂傛偔丄乽峧媑偺帪戙偺姩掕嬦枴栶丄壃尨廳廏偑峴偭偨夵拻偼丄嬥嬧偺昳埵傪壓偘丄偦偺弌栚乮夵拻偵傛傞梋忚暘乯偱枊晎偺埆壔偡傞嵿惌傪曗偍偆偲偟偨乿偲偝傟傞偑丄尩枾偵偼丄尦榎偺夵拻偼丄嬥壿偱宑挿彫敾偺廳偝3暘偺2丒昳埵84亾偐傜57亾偵丄嬧壿偼昳埵80亾偐傜64亾傊偲偄偆撪梕偺傕偺偱偁偭偨丅堷偒壓偘暆偑彫偝偐偭偨嬧壿偑戅憼偝傟丄嬧崅嬥埨偱暔壙偺忋徃傪傕偨傜偟偨偑丄慡懱偺棳捠捠壿検偑憹戝偟偨偙偲偐傜丄捠壿晄懌偺娚榓偵戝偒偔婑梌偟偨揰傕偁偭偨偙偲偼尒摝偣側偄丅
丂師偺怴堜敀愇偑峴偭偨丄惓摽偺夵拻偼丄嬥壿偱宑挿彫敾偲摨昳埵偺84亾傊偺暅婣傪恾偭偨偑丄偦傟傪壓夞傞偲偄偆晽昡偑偨偭偨偙偲偐傜丄梻擭偺嫕曐偺夵拻偱偼丄埿怣堐帩偺偨傔嬥壿偺昳埵傪偝傜偵87亾偵堷偒忋偘偨丅偦偺寢壥丄棳捠捠壿検偼愨懳揑偵弅彫偟丄怺崗側僨僼儗傪彽偄偨丅嬤徏栧嵍塹栧偺乽慮崻嶈怱拞乿偵戙昞偝傟傞怱拞傕偺偑岲昡傪攷偟偨偺偼丄偙偆偟偨攚宨偑偁偭偨偺偱偁傞丅
丂師偺摽愳媑廆偑峴偭偨尦暥偺夵拻偼丄彫敾偺昳埵傪65亾傊乮嬥偺娷桳検偐傜偡傟偽嫕曐彫敾偺敿暘乯丄挿嬧偺昳埵傪46亾傊棊偲偟偨傕偺偩偑丄媽彫敾侾枃偵尦暥彫敾1丏65枃偲偄偆憹曕岎姺傪峴偄丄偦偺棳捠懀恑偵廳揰傪抲偄偨丅捠壿偺棳捠検偼偦傟傑偱偺40亾傕憹戝偟丄揔搙偺僀儞僼儗岠壥傪傕偨傜偟丄埲屻丄尦暥婜偺嬥嬧壿偼80擭偺挿婜偵傢偨偭偰埨掕偡傞偙偲偵側傞丅
嬥壿杮埵惂偺帋傒亅揷徖偺夵妚
丂傛偔丄乽搶崙偺嬥尛偄丄惣崙偺嬧尛偄乿偲尵傢傟傞丅峕屗偱偼丄悢検壿暭偲偟偰偺嬥乮彫敾乯丄忋曽偱偼攭検壿暭偲偟偰偺嬧乮挌嬧偲摛斅嬧乯偲偄偆慡偔惈奿偺堎側傞棳捠壿暭偺堘偄傪巜偟偰偺尵梩偩偑丄尦乆丄惣擔杮偱偼拞崙偲偺杅堈偵嵺偟丄嬧偑屆偔偐傜寛嵪庤抜偲偟偰梡偄傜傟偰偒偨楌巎揑揱摑傪枊晎偑捛擣偣偞傞傪摼側偐偭偨偙偲偐傜惗傑傟偨傕偺偱偁偭偨丅枖丄墱廈傗嵅搉側偳嬥偺嶻抧偑搶崙偵懡偔丄娾尒側偳偺嬧偺嶻抧偑惣崙偵懡偄偲偄偆帠忣傕偁偭偨傠偆丅峕屗偺憡杘庢傝傪廫椉庢傝偲偄偄乮廫椉偲偼侾擭娫偺媼椏偑廫椉偺憡杘庢傝偺偙偲乯丄忋曽偱偼壗廫栨庢傝偲徧偟偨偺傕偙偆偟偨帠忣偵傛傞丅
丂
丂揷徖堄師偼偙偆偟偨忬嫷傪懪奐偡傋偔丄嬥壿杮埵惂傊岦偗巚偄愗偭偨壿暭惌嶔傪峴偭偨丅愭偢丄擔杮嵟弶偺寁悢嬧壿偱偁傞柧榓屲栨嬧偺敪峴丅摉帪丄1椉亖嬧60栨乮栨偼廳偝偺扨埵乯偱偁偭偨偐傜丄屲栨嬧偼12暘偺1椉偺壙抣傪桳偡傞偙偲偵側傞丅偲偙傠偑丄昳埵偑46亾偲挊偟偔楎偭偰偄偨偙偲偐傜椉懼彜偺斀懳偐傜棳捠偣偢幐攕丅偙偺嬯偄嫵孭傪摜傑偊偰敪峴偝傟偨偺偑撿鑐擇庨嬧乮1椉亖4暘亖16庨偩偐傜丄偙傟8枃偱1椉乯丅
丂撿鑐偲偼丄拞悽埲棃丄椙幙偺嬧傪堄枴偡傞尵梩偱偁偭偨偑丄偙傟偼昳埵偑柧榓屲栨嬧偺栺2攞偺98亾偲偄偆崅昳埵乮傎偲傫偳弮嬧乯偱丄揷徖偼椉懼彜偺斀懳偵傕娭傢傜偢丄柍棙巕丄柍扴曐丄嶰擭晩偲偄偆攋奿偺忦審偱戄偟晅偗丄偦偺棳捠偺懀恑傪恾偭偨丅尦乆丄廳偝偱庢傝堷偒偝傟偰偄偨嬧壿偺寁悢壔偼丄摉帪偺擔杮偺嬥梈傪嬥壿杮埵惂搙傊堦杮壔偡傞忋偱廳梫側僀僲儀乕僔儑儞偱偁偭偨丅場傒偵丄揷徖偺帪戙傪愭庢傝偟偨宱嵪惌嶔偼丄尨椏偺嬧偺挷払偵傕尒傜傟丄偦傟傑偱偺條偵媽壿傪拻偮傇偟偰摼傞偺偱偼側偔丄摵傗昒暔乮僼僇僸儗傗偄傝偙乯傪桝弌偟偰丄拞崙傗僆儔儞僟偐傜桝擖偟偨傕偺偱偁偭偨丅拞崙偐傜擖偭偨偺偼丄攏掻嬧傗僗儁僀儞偺僪儖嬧壿丄僠儀僢僩傗埨撿偺嬥嬧丅僆儔儞僟偐傜偼僨硟J僢僩嬥壿傗僨硟J僩儞嬧壿丅
丂枖丄揷徖偺帪偵敪峴偝傟偨擔杮嵟弶偺戝慘丄姲塱捠曮巐暥慘偼丄摵埲奜偵垷墧24亾丄庎8亾傪崿擖偟偨恀鐹慘偱偁偭偨偑丄偦偺垷墧偝偊傕拞崙偐傜桝擖偟偨傕偺偱偁偭偨乮巐暥慘偺儌僨儖偼姡棽捠曮摍偺惔挬慘偱偁偭偨乯丅摉帪丄揝慘偺慹埆偝偵鐒堈偟偰偄偨堦斒弾柉偼丄傓偟傠偙偺巐暥慘傪娊寎偟偨丅撿鑐擇庨嬧偼揷徖幐媟屻傕拻憿偝傟丄埲屻丄枊枛傑偱7庬椶偺寁悢嬧壿偑敪峴偝傟丄1830擭戙偵偼丄嬧壿偺9妱偑寁悢嬧壿偱愯傔傜傟丄枊枛偵偼揤曐堦暘嬧乮4枃偱1椉乯偑捠壿偺庡棳偲側偭偰偄偭偨丅寁悢嬧壿偺晛媦偲嫟偵丄擔杮偵偍偗傞嬥嬧斾壙偼崙嵺憡応乮1丗15乯傪忋夞傞1丗6傑偱愙嬤偟偰偄偨丅幚偼偙傟偑丄屻偺丄奐崙屻偺嬥偺戝検棳弌偺暁慄偲側偭偰偄偔偺偱偁傞丅
奐崙偺棊偲偟巕亅枩墑彫敾
丂奐崙帪丄崙嵺揑偵偼拞撿暷偺僪儖嬧壿偑杅堈寛嵪梡偵梡偄傜傟丄崙撪偱偼揤曐堦暘嬧偑捠壿偺庡棳傪愯傔偰偄偨丅1854擭丄擔暷娫偱1僪儖嬧壿亖1暘嬧1枃丄乮彫敾1枃亖1僪儖嬧壿4枃乯偺岎姺儗乕僩偑掕傔傜傟偨偑丄屻偵暷崙憤椞帠僴儕僗偵傛傞丄抧嬥乮廳偝乯偵傛傞岎姺偵枊晎偼孅偟丄埲屻丄1僪儖嬧壿亖1暘嬧3枃偺岎姺儗乕僩偑愝掕偝傟偨丅摉帪偺嬥嬧斾壙偼丄擔杮崙撪偱偼1丗4.6丄奀奜偱偼1丗16偲丄嬧偺斾壙偑栺3攞崅偐偭偨偙偲偐傜丄奐峘抧偱偼丄奜崙杅堈彜偑僪儖嬧壿偲堦暘嬧傪岎姺偟丄偦傟傪彫敾偲堷偒懼偊丄偦傟傪奀奜偵帩偪弌偟偰嵞傃嬧偵岎姺偡傞偩偗偱丄3攞傕偺棙塿傪摼偨丅
丂偙偺娫丄奐峘敿擭偱奀奜偵棳弌偟偨嬥偼丄30乣40枩椉丄偦傟偼丄埨惌偺夵拻偱搊応偟偨埨惌彫敾偺拻憿検35枩椉梋傝偵傎傏旵揋偡傞乮嬥壿棳捠崅偺栺2亾偵傕払偟偨乯丅埨惌彫敾偺尰嵼偺帪壙偑摿偵崅偄偺偼丄崙撪偵巆偭偨傕偺偑彮側偔奀奜偱傕傎偲傫偳拻偮傇偝傟偰偟傑偭偨偐傜偱偁傞丅偦偙偱枊晎偼丄僪儖嬧壿偲1暘嬧偲偺岎姺傪嬛巭偡傞堦曽丄揤曐丄埨惌彫敾偺懳嬧壿捠梡壙抣傪3攞偵堷偒忋偘丄枩墑尦擭乮1860擭乯丄昳埵57亾丄廳偝3暘偺1偺枩墑彫敾傪敪峴偟偰嬥偺棳弌傪杊偄偩丅側偍丄枩墑彫敾偼媽壿偲憹暘岎姺乮媽壿偵2攞偺僾儗儈傾儉乯偺忋丄岎姺偝傟偨寢壥丄枊枛偺僀儞僼儗傪彽偒丄廃抦偺傛偆偵懜墹澋埼塣摦偺寖壔傪彽偔偙偲偵側傞丅
懢惌姱嶥丒柉晹徣嶥
丂柧帯偺怴惌晎偼丄嬥傕側偗傟偽孯戉傕側偐偭偨惌尃偱偁偭偨丅懢惌姱嶥偼宑墳巐擭偵廫椉丄屲椉丄堦椉丄堦暘丄堦庨偺寁俆庬椶丄柉晹徣嶥偼梻擭偺柧帯擇擭偵擇暘丄堦暘丄擇庨丄堦庨偺寁係庬椶偑偦傟偧傟敪峴偝傟偨丅懢惌姱嶥偺敪埬偼丄暉堜斔巑嶰壀敧榊乮屻偺桼棙岞惓乯丅丂巌攏椛懢榊偺乽棿攏偑備偔乿偺嵟廔姫偱昤偐傟偰偄傞傛偆偵丄棿攏偲偺弌夛偄偑摉帪丄暵偝傟偰偄偨嶰壀偺怴惌晎弌巇偵偮側偑偭偨丅
丂懢惌姱嶥偼摉帪丄乽嬥嶥乿偲屇偽傟偨偑丄怋嶻嫽嬈偺帒嬥偵偲偄偆嶰壀偺慱偄偲偼棤暊偵丄怴惌晎偺崙屔偺曗揢偲朿戝側孯帒嬥偵梡偄傜傟乮夛捗愴憟偼偙偺擭偺9寧偵廔傢偭偨乯丄嬥嶥偺幮夛揑側怣梡偼掅偔丄堦帪丄惓壿100椉偵懳偟偰嬥嶥166椉傑偱壓棊偟偨丅寢嬊丄憤妟4800枩椉偺懢惌姱嶥偑敪峴偝傟偨偑丄暉壀丄廐揷丄峀搰丄崄峘偱傕婁憿偑峴傢傟丄柧帯屲擭偵敪峴偝傟偨柧帯捠曮嶥偵彊乆偵岎姺偝傟偦偺巊柦傪廔偊偨丅丂
丂庼嬈偱偼丄摿偵懢惌姱嶥偺棤柺乽宑墳曡扖敪峴乿偵拲栚偝偣棙梡偟偰偄傞偑丄杮暔偺懢惌姱嶥傗柉晹徣嶥偼丄曐懚忬懺偵傕傛傞偑丄懠偺巻暭摨條丄妟柺偺彫偝側傕偺偱偁傟偽5愮墌埵偱擖庤偱偒傞丅側偍丄懢惌姱嶥偺僨僓僀儞偼丄嫗搒偺摵斉挙崗巘徏揷撝挬偺庤偵側傞傕偺偱偁傞乮斵偼弶婜偺庤挙傝愗庤傗巻暭偺尨恾嶌惉偵妶桇偟偨乯丅
墌偺抋惗
丂柧帯巐擭乮1871擭乯丄乽怴壿忦椺乿偺岞晍偵傛偭偰丄擔杮偼嬥杮埵惂搙傪嵦梡偟丄暷崙嬥壿1僪儖亖1墌嬥壿偑杮埵壿暭偵掕傔傜傟偨丅偦偺慜擭傑偱丄惌晎撪晹偱偼丄嬧杮埵惂搙偺嵦梡偑撪掕偝傟偰偄偨偑丄嬥杮埵惂搙傊偺曽岦揮姺偼丄嬥梈惂搙挷嵏偺偨傔搉暷偟偰偄偨埳摗攷暥偺寶媍偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅偙傟偼丄摉帪丄墷暷彅崙偑嬥杮埵惂偵堏峴偡傞偲偄偆崙嵺忣惃傪摜傑偊偨傕偺偱偁偭偨偑丄幚偼峕屗帪戙偺壿暭惂搙偺楢懕惈偵傕怺偔攝椂偟偨慬抲偱偁偭偨丅
丂偲偄偆偺偼摉帪偺婎幉捠壿偱偁偭偨枩墑擇暘嬥擇枃亖堦椉亖暷崙1僪儖偲尒側偝傟偰偄偨丅怴惌晎偼偦偺枩墑擇暘嬥乮弮嬥0丏7g乯傪儌僨儖偵1墌嬥壿乮弮嬥1丏5g乯傪拻憿偟丄侾墌嬥壿亖梞嬧侾枃偱偁傞偲掕傔丄堦椉亖堦墌傊偺僗儉乕僗側曄姺傪峴偭偨丅枖丄偦傟傑偱偺巐恑朄偵曄偊偰廫恑朄傪嵦梡偟偨偺偼寁嶼柺偱偺棙曋惈傪摜傑偊偰偺偙偲偩偭偨偑丄慘丄椥偲偄偆屇徧偼暷崙偺僙儞僩丄儈儖偵偪側傫偩傕偺偩偭偨丅枖丄墌偲偄偆屇徧偼丄尦乆拞崙偱墌偼椉偲摨偠堄枴偱梡偄傜傟偰偍傝丄墌偑搶撿傾僕傾杅堈偺寛嵪偵梡偄傜傟偰偄偨嬧壿偺屇徧偱偁偭偨偙偲側偳偵桼傞丅
丂庼嬈偱偼丄杮暔偺堦墌嬥壿傪帩偪崬傒偨偄偲偙傠偩偑梋傝偵傕崅壙側偺偱丄乽怴壿忦椺乿偺崕柧側恾埬偱戙懼偟偰偄傞丅恾偵偁傞傛偆偵偦傟偼旤弍揑側娤揰偐傜尒偰傕愨柇側僨僓僀儞偲嵶枾側媄弍偐傜側傞傕偺偩偑丄扴摉偟偨偺偼峕屗偺搧憰嬶偺惂嶌傪偟偰偄偨壛擺壞梇偲偦偺岺朳偺怑恖払偱偁偭偨丅偍屬偄奜崙恖偺僂祦[僩儖僗偑丄挙傝忋偑偭偨崗報傪尒偰愩傪姫偄偨偲偄偆榖偑巆偭偰偄傞偑丄壞梇偼屻偵搶嫗旤弍妛峑乮尰嵼偺寍戝乯偱嬥岺傪嫵偊丄掗幒媄寍堳偵傕悇偝傟摍丄嬥岺壠偲偟偰柤傪側偟偨丅
媽崙棫嬧峴寯
丂柧帯屲擭乮1872擭乯丄怴惌晎偼暷崙偺僫僔儑僫儖僶儞僋偺惂搙傪庢傝擖傟丄崙棫嬧峴忦椺傪惂掕偟丄惓壿偲偺橻姺傪媊柋偯偗偨崙棫嬧峴偺愝棫傪峴偭偨丅尵偆傑偱傕側偔丄崙棫嬧峴偼丄崙桳嬧峴偱偼側偔崙朄偵傛偭偰愝棫偝傟偨巹棫嬧峴傪巜偡丅巻暭偺報嶞偼暷崙偺僐儞僠僱儞僞儖丒僶儞僋僲乕僩丒僇儞僷僯乕偵敪拲偟丄暷崙偐傜摓拝偟偨巻暭偵嬧峴柤丄強嵼抧丄摢庢柤傗巟攝恖柤傪巻暭椌乮屻偺憿暭嬊乯偱壛嶞偝傟奺嬧峴偺帒杮嬥偵墳偠偰攝傜傟偨丅摉弶丄崙棫嬧峴偵偼橻姺偑媊柋偯偗傜傟乮帒杮嬥偺40亾傪嬥嬧壿偵丄60亾傑偱偺崙棫嬧峴巻暭偺敪峴偑擣傔傜傟偨乯偨偙偲偐傜丄愝棫傪怽偟弌傞幰偑彮側偔丄嬐偐4峴偵巭傑偭偨堊丄柧帯嬨擭丄橻姺媊柋傪柶彍偟晄姺巻暭偺敪峴傪擣傔偨寢壥丄愝棫婓朷幰偑憡師偓丄嵟廔揑偵153傕偺崙棫嬧峴偑抋惗偟偨丅柧帯嬨擭偲偄偊偽丄壺巑懓偺壠榎傪慡攑偝傟偨擭偵偁偨傞丅偦偺嵺丄岎晅偝傟偨嬥榎岞嵚徹彂摍傪崙棫嬧峴巻暭偺堷偒摉偰偵弌棃傞偙偲偵傛傝丄壺巑懓偺弌帒偵傛傞摿戝婯柾偺戞廫屲崙棫嬧峴偑愝棫偝傟偨丅
丂庼嬈偱偼丄暋惢偺崙棫嬧峴寯傪帩偪崬傒丄嬧峴寯偺昞棤偵婰嵹偝傟偰偄傞戞仜仜崙棫嬧峴偺売強偵拲栚偝偣偰巊偭偰偄傞丅尰嵼偺戞巐丄戞幍廫幍嬧峴偼崙棫嬧峴帪戙偺柤巆偱偁傞丅丂媽崙棫嬧峴寯偺尨夋偼擔杮恖偺庤偵側傞傕偺偱丄恾偵偁傞傛偆偵丄慺滬歫懜偲敧婒偺戝幹丄恄岟峜岪偺嶰娯惇敯丄怴揷媊掑偲帣搰崅摽丄尮堊挬偲尦泟偲丄楌巎揑側戣嵽偑懡偔梡偄傜傟偨丅偙傟傜偺巻暭偑敪峴偝傟偨柧帯榋擭乮侾俉俈俁擭乯偲尵偊偽丄惇娯榑偑暒摣偟偰偄偨擭偵偁偨傞丅
丂惇娯榑偼丄怴惌晎偑丄峕屗帪戙傑偱偺挬慛偲懳攏偲偺挬峷娭學傪傛偔挷嵏偡傞偙偲側偔丄偄偒側傝挬慛偲偺崙岎傪媮傔傛偆偲偟丄挬慛懁偑擔杮偺懜戝偝傪旕擄偟偨偙偲偐傜暒偒婲偙偭偨傕偺偱偁偭偨偑丄偙偺帪婜偵偁偊偰丄楌巎揑帠幚偱偼側偄丄恄岟峜岪偺嶰娯惇敯傪恾埬偵嵦梡偟偨偺偼丄柧傜偐偵崙壠偺堄巚偵婎偯偄偨傕偺偱偁偭偨丅偦偆尵偊偽慺滬歫懜偺敧婒偺戝幹戅帯傗尮堊挬丒尦泟傕丄嫟偵奜惇傪僀儊乕僕偝偣傞恾埬偺傛偆偵尒偊傞偺偩偑丒丒丒丅
巻暭偺拞偺徰憸
丂徰憸擖傝巻暭戞堦崋偼丄柧帯14擭敪峴偺恄岟峜岪堦墌寯偱偁偭偨乮埲屻丄摨偠徰憸偱堦擭枅偵屲墌寯丄廫墌寯偑敪峴偝傟偨乯丅偙偺巻暭乮夵憿巻暭乯偑敪峴偝傟偨攚宨偵偼丄柧帯俆擭偵敪峴偝傟偨柧帯捠曮嶥偑丄戝偒偝丄僨僓僀儞偺揰偱寯庬偑嬫暿偝傟偵偔偐偭偨偙偲偵壛偊丄梡巻偺惈幙忋丄嵤怓偺僀儞僋偑怹摟偣偢丄偁傞庬偺栻昳偵傛傝抧柾條偑曄怓丄傕偟偔偼徚柵偟偰偟傑偆堊丄梕堈偵妟柺偑曄憿偱偒傞偲偄偆栤戣偑偁偭偨偲偝傟偰偄傞丅徰憸擖傝巻暭偼愭偢戞堦偵婾憿杊巭偵栚揑偑偁偭偨偺偱偁傞丅
丂恾埬丒尨斉惂嶌偵偁偨偭偨偺偼丄僪僀僣偺僪儞僪儖僼夛幮偵嬑柋偟偰擔杮偺巻暭傪惢嶌偟偰偄偨僀僞儕傾恖僄僪儚儖僪=僉僆僜乕僱偱偁偭偨乮柧帯8擭丄惌晎偵傛傝彽偐傟傞乯丅側偤丄恄岟峜岪偑慖偽傟偨偺偐偵偮偄偰偼晄柧偩偑丄尰嵼偺傛偆偵幨恀惢斉偺媄弍偑側偐偭偨摉帪丄巻暭偲摨偠戝偒偝偺摵斉偵價儏儔儞偲屇偽傟傞挙崗搧偱捈挙傝偟偰墯斉報嶞偱巇忋偘傜傟偨傕偺偩偑丄尰嵼偐傜尒偰傕恄岟峜岪偺婄棫偪偑惣梞恖偭傐偔尒偊傞偺偼丄嵍忋偐傜岝傪偁偰傞堦揰岝尮朄偲偄偆惣梞媄朄傕偝傞偙偲側偑傜丄昤偄偨僉僆僜乕僱帺恎偑奜崙恖偱偁偭偨偐傜偵懠側傜側偄丅偦偺惂嶌偵偁偨偭偰偼乽梒偵偟偰憦柧塨抭丄梕杄憇楉乿偲偄偆擔杮彂婭偺婰弎傪嶲峫偵偟丄摉帪丄巻暭椌偵嬑柋偟偰偄偨彈巕峴堳悢柤傪儌僨儖偵偟偨偲傕尵傢傟傞丅側偍丄僉僆僜乕僱偼丄柧帯廫敧擭敪峴偺丄擔杮嵟弶偺嬧橻姺寯偺戝崙庡柦偺恾埬傪偼偠傔丄柧帯擇廫擭戙偵敪峴偝傟偨嬧橻姺寯偵師乆偵搊応偟偨丄晲撪廻擧丄摗尨姍懌丄榓婥惔杻楥丄悰尨摴恀偺徰憸僔儕乕僘傕庤偑偗偰偄傞乮廃抦偺捠傝丄柧帯揤峜丄嶰忦幚旤丄惣嫿棽惙丄栘屗岶堯丄戝媣曐棙捠摍偺徰憸夋偼慡偰僉僆僜乕僱偺庤偵側傞傕偺偱偁傞乯丅
丂偦偺恖暔偺慖掕偵偁偨偭偰偼妕媍偵偐偗傜傟屻丄揤峜偺嵸壜傪摼偰敪峴偝傟偨偑丄偦偺徰憸偺帪戙峫徹偵偁偨偭偰偼丄巻暭徰憸偺嫵堢岠壥傪慱偭偰丄旤弍巎丒擔杮巎偺愱栧壠崟愳恀棅偵埶棅偑偁偭偨丅枖丄巹偺悽戙偵撻愼傒怺偄惞摽懢巕偺徰憸偑弶傔偰巻暭偵搊応偟偨偺偼丄徍榓屲擭乮昐墌寯乯偺偙偲偱偁偭偨偑丄偦偺嵺丄帎栤偵梐偐偭偨偺偼丄擔杮巎妛幰崟斅彑旤偲峫屆妛幰偺崅嫶寬偱偁偭偨丅側偍丄搶栰帯擵巵偑慜宖彂偱弎傋偰偄傞傛偆偵丄摗尨姍懌偺徰憸偼丄廬棃尵傢傟偰偄傞傛偆偵丄儌僨儖偼徏曽惓媊偱偼側偔丄尛搨巊媑巑挿扥偱偁偭偨壜擻惈偑崅偄丅徻偟偔偼丄惀旕丄偦偺挊彂傪偍撉傒偄偨偩偒偨偄丅
丂崱傑偱偦偺徰憸偑嵟傕懡偔巻暭偵搊応偟偨偺偼壗偲尵偭偰傕惞摽懢巕偱7夞傪悢偊傞丅枖丄巻暭偲愗庤偺椉曽偵搊応偟偨偺偼丄2004擭偐傜搊応偡傞栰岥塸悽丄旙岥堦梩傪娷傔丄惞摽懢巕丄恄岟峜岪丄摗尨姍懌丄暉戲桜媑丄怴搉屗堫憿丄壞栚燍愇偺8柤偱偁傞丅側偍丄尰峴偺壞栚丄怴搉屗丄暉戲偺慖掕偵偁偨偭偰偼丄
丂幚嵼偺恖暔偱嬈愌偑偁傝抦柤搙偑崅偄偙偲丅
丂巎幚峫徹柺偱柧妋側幨恀傗徰憸夋偑偁傞偙偲丅
丂寍弍壠傗暥壔恖偺嵦梡偑嬤擭偺悽奅揑側挭棳偵側偭偰偄傞偙偲丅
丂崙嵺惈偑偁傞偙偲丅
丂偙傟傜3寯庬偼摨帪報嶞偱偁偭偨偨傔丄3寯庬摑堦僥乕儅偱慖傇偙偲丅
丂柉娫傾儞働乕僩挷嵏偱暥壔恖偺婓朷妱崌偑崅偐偭偨偙偲丅
摍偑峫椂偝傟丄嵟廔揑偵偼嵿柋徣報嶞嬊偺僨僓僀儞丄挙崗偺愱栧壠偺堄尒傕偁偭偰寛掕偝傟偨偲尵傢傟傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
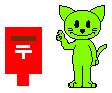 偛堄尒偛姶憐偼偙偪傜傑偱
偛堄尒偛姶憐偼偙偪傜傑偱丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂